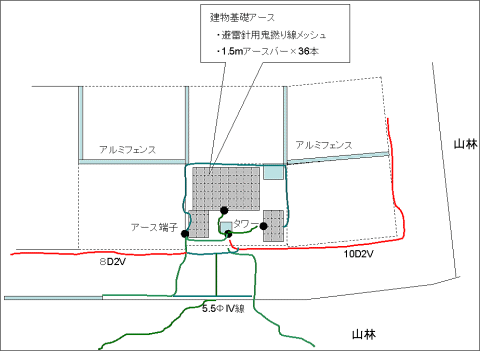アース改良工事
当局は小高い山の上にあり、ロケーション的には良いのですが、地盤が山地特有の山土と岩石でアースの設置が問題でした。特にローバンドを運用する上で長年の課題でした。そんな折家の建て替えを行うことになり、ハウスメーカーの協力により、家の基礎工事に合わせて接地電極を埋設することができ、アースの改良を行うことが出来ましたのでレポートいたします
まず最初に過去に工事したアース施工工事を参考にして工事しました。
◆<施工例1〜山頂の無線中継局>
無線中継局の施工に際して、基礎工事前に接地工事に取り掛かる。が、思いの他、接地抵抗が落ちず、基礎工事の砕石敷きが終了した時点で基礎一面に裸銅線でグリッドを組み、張り巡らした。翌日、コンクリートはそのまま打設。コンクリート乾燥後、再び、接地抵抗を計測すると、思いのほか低い接地抵抗が得られた。
◆<施工例〜砂地の上のレコーディングスタジオ>
砂地にアースを落とすことに関して、技術的に非常に困難な状況が予想されたため、構造体接地を提案。鉄筋コンクリート造の建物の鉄筋に接地線を接続。結果として接地抵抗の低減とともにオーディオ用の良質なアースとして機能させることができた。
工事のステップ
1,接地電極の工事
2,接地電極の配置
3,ラジアルアース
1,接地電極の工事。

① 基礎工事により基礎溝が地表より50cmほど掘削掘されます。それに合わせてIV線を接続したアース電極を埋設します。
②アース電極には10本ほどは正式?の1.5mアース棒を使いましたが、配電盤に使用する電極導体バーの廃材が手に入ることとなり大半はこれを利用しました。
電極導体バーの長さは1.5m〜1mと様々ですが巾40mm、厚さ5mmと正式?のアース棒より良好なアースが取れそうな感じです。
接地電極の周りの土壌には接地抵抗低減材?として粉木炭を使し埋設しました。

③アースバーを埋める竪穴は地盤改良等で使用する建設メーカーの竪穴ドリルで掘削してアースバーと粉木炭を入れましたが、場所によっては岩に当たって掘れない場所があり、この場所では電極を水平に設置しました。

④アースバーを埋めた上に基礎のベースとなる砕石を敷き詰め圧縮。
砕石上に40Φの避雷針用の鬼より銅線を基礎の溝すべてにメッシュ状に配線します。

⑤アース電極から出ているリード線を鬼より銅線に接続していきます。
⑥建物基礎の鉄筋に躯体アース用のリード線を接続して地上に躯体アースリード線を出しておきます。
戻る
2,接地電極の配置(建物基礎アース)
 ①接地電極は基礎の溝に合わせて敷地内に合計30本ほど埋設し、上部のメッシュ状の鬼より銅線に接続してあります。
①接地電極は基礎の溝に合わせて敷地内に合計30本ほど埋設し、上部のメッシュ状の鬼より銅線に接続してあります。
②シャックの直近、とタワー直下、の2か所にアース電極ターミナルを設けてにすべてのアースリード線を集合してあります
※工事中のアースターミナル

。
戻る
戻る
3,ラジアルアース
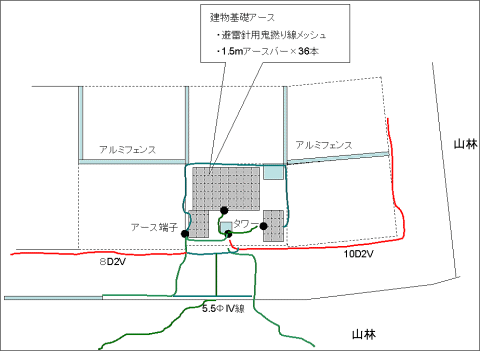
さらに160mバンドの飛び?を少しでも改良するためにタワーの周りにラジアルアース・・(もどき)を敷設し、タワー下のアースターミナルにつなぎました。
①タワー周りの側溝に古くなって撤去した同軸ケーブルを這わせました
。
②前の山林の中に5.5ΦIV線又は2mm裸銅線を地中に埋めて張りました。
③タワー近くの金属製フェンスおよび金属製の物入、ガレージを5.5ΦIV線でタワー下のアースターミナルにつなぎました。
4,飛びの確認
冬場の1シーズンだけ早朝運用しましたが聞こえていれば、確実に応答をもらえるようになりました。
しかしながら、各局がコールしてるのに、聞こえなければ呼べません。
受信の改良が今後の課題です。
戻る





 ①接地電極は基礎の溝に合わせて敷地内に合計30本ほど埋設し、上部のメッシュ状の鬼より銅線に接続してあります。
①接地電極は基礎の溝に合わせて敷地内に合計30本ほど埋設し、上部のメッシュ状の鬼より銅線に接続してあります。